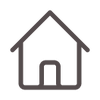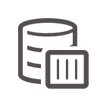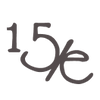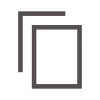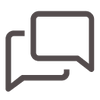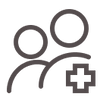監修 :栄養士 OKAYU
梅干しは”万能薬”?栄養成分と期待される効果を15/eの栄養士が徹底解説!

梅干しは、独特の酸っぱさとクセになる塩味でつい食べたくなる、日本の伝統的な漬物の一種です。
古くから体にいいと重宝されてきましたが、実際に梅干しを食べることで、どのような健康への働きかけがあるのでしょうか?
この記事では、梅干しの栄養成分や効果・効能に加えて、おすすめの食べ方や注意点についてご紹介します。
目次
- 梅干しに期待できる効果・効能
- 梅干しのデメリット|食べるときの注意点は?
- 梅干しの効果的な食べ方|いつ食べるとよい?
- 梅干しの効果効能を健康・美容に活かそう
梅干しに期待できる効果・効能

まずは梅干しに含まれる栄養成分、梅干しに期待できる効果・効能を解説します。
疲労回復を促す
梅干しが酸っぱいのは、クエン酸などの有機酸が含まれているためです。
このクエン酸には、疲労回復を促進する効果が期待できます。
体を動かすエネルギーのもとになる栄養素は、主に糖質です。
激しい運動をすると、糖質からエネルギーが作られる過程で乳酸という物質が生成されます。
運動後に疲労を感じるのは、筋肉に乳酸が蓄積されることが原因の一つと言われています。
クエン酸の働きのひとつに、乳酸の分解を促進する作用があるため、クエン酸を摂取すると疲労回復が促されると考えられています。
骨を丈夫にする
梅干しのクエン酸は、強い骨を作るために欠かせないカルシウムの吸収にも関わることが分かっています。
カルシウムは骨を構成する重要なミネラルですが、吸収率はあまり高くありません。
しかしクエン酸には、カルシウムを体に吸収しやすい形に変える「キレート作用」があります。
そのため、クエン酸を含む梅干しはカルシウムの吸収率を高め、強い骨づくりに役立つと考えられています。
自律神経を整える
梅干しにより吸収が促進されるカルシウムは、自律神経の働きにも影響を与えるでしょう。
自律神経は、呼吸や体温調節など、生命維持に欠かせない体の機能を調整する神経です。
自律神経では交感神経と副交感神経がバランスをとって働いていますが、このバランスが乱れると体に不調が現れることがあります。
カルシウムには神経の興奮を抑える働きもあります。
そのため、過度に作用している交感神経の興奮をカルシウムにより抑えることで、自律神経が整うことが期待できるでしょう。
消化を助ける
梅干しを食べたときに口の中で大量に分泌される唾液には、消化酵素が含まれています。
唾液に含まれるアミラーゼは、でんぷんを分解して消化しやすい形に変える働きがある消化酵素です。
アミラーゼによって分解されたでんぷんは、体内でブドウ糖にまで分解され、体を動かすエネルギーとして利用されます。
ご飯(米)には、でんぷんが豊富に含まれています。
そのため、ご飯と一緒に梅干しを食べることは、ご飯の消化を助ける意味で理にかなった食べ方といえるでしょう。
肝臓の機能をサポートする
梅に含まれる有機酸のひとつに、ピクリン酸があります。
肝臓の機能をサポートして代謝を高めることは、ピクリン酸の作用のひとつです。
この作用により、梅干しは二日酔い防止の効果が期待できると考えられています。
お酒を飲んで二日酔いになるのは、アルコールの分解物であるアセトアルデヒドを肝臓で十分に処理できなくなるためです。
アセトアルデヒドには毒性があり、血中濃度が高まると頭痛や吐き気、胃もたれなどの二日酔いの症状が現れます。
ピクリン酸を含む梅干しを食べると肝臓の機能が高まり、アセトアルデヒドの分解が進むため、二日酔いの症状緩和に役立つでしょう。
ダイエット効果を高める
梅干しに含まれるバニリンという成分の働きのひとつに、脂肪の燃焼を促す作用があります。
そのため、梅干しを食べるとダイエット効果を高めることが期待できます。
体に吸収されたバニリンは脂肪細胞を刺激します。
その刺激により脂肪の燃焼が促進されて脂肪細胞が小さくなると言われています。
バニリンを効率よく摂取するなら、梅干しを加熱してから食べるのがおすすめです。
研究によると、バニリンは加熱により増加することが分かっています。
梅干しを電子レンジで加熱したり、炒め物や煮物に加えたりすることでバニリンが増加するため、ぜひお試しください。
※梅干しを加熱しすぎると破裂することもあります。
特に電子レンジは、時間と温まり具合を確認しながらお試しください。
風邪を予防する
梅干しを食べると、代謝が活発になり、血流が改善されて免疫機能が高まり、風邪などの感染症を予防できると考えられています。
梅干しの成分であるムメフラールにはさまざまな作用があります。
血液中の血小板の凝集を抑えることで、血栓の形成を防ぐ作用もそのひとつです。
また、ムメフラールには赤血球が形を変える能力を高め、毛細血管を通過しやすくする作用もあります。
ムメフラールのこれらの作用により血流が改善されると、代謝が高まります。
すると体温が上がるため免疫機能も向上し、風邪などの感染症から体を守る力が高まることが期待できます。
なお、ムメフラールも加熱により増加することが分かっています。
梅干しを電子レンジで温めたり料理に加えたりして、ムメフラールを効率よく摂取してみてくださいね。
胃の健康を保つ
梅干しは、ピロリ菌による胃炎を防ぐことで胃の健康維持に役立つと考えられています。
ピロリ菌は胃に生息する細菌です。
ピロリ菌に感染すると一部の人は胃炎を発症し、胃炎から胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんに進行する可能性があります。
梅干しに含まれる梅リグナンという成分には、ピロリ菌の活動を抑制する作用が期待できます。
ピロリ菌による胃炎を防いで胃の健康を守るためには、梅干しを食べるとよいでしょう。
肌を美しく保つ
梅干しの梅リグナンは、肌の美しさに関わる成分でもあります。
肌にシミやしわができる原因のひとつは、体内に活性酸素が増加して肌が酸化されるためです。
梅リグナンには、活性酸素を除去して体を酸化から守る抗酸化作用があることが分かっています。
そのため、梅干しの摂取はシミやしわの予防につながると考えられます。
梅干しのデメリット|食べるときの注意点は?

さまざまな効果・効能がある梅干しですが、塩分量が多いため、食べすぎには注意が必要です。
塩分の過剰摂取は、体のむくみや高血圧の原因になります。
梅干し1粒(15g)の塩分量は、昔ながらの塩漬けの場合で2.3g、調味液に漬けた塩分控えめのものでも1.0gあります。
(※梅干し1粒(15g)の可食部12.75gにて算出)
厚生労働省による「日本人の食事摂取基準」で推奨されている1日の塩分摂取目標量は、成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満です。
梅干し以外の食事にも塩分が含まれているため、梅干しを毎日何粒も食べていると健康に悪影響が及ぶおそれがあります。
したがって、梅干しを毎日食べるのは1日1粒までを目安にしましょう。
梅干しの効果的な食べ方|いつ食べるとよい?

梅干しを食べるおすすめのタイミングは次のとおりです。
- 運動前後
- 疲れを感じたとき
- お酒を飲むとき
梅干しには筋肉疲労を回復させる効果が見込めます。
そのため、筋肉を使う運動前後のほか、体を動かして疲れを感じたときに食べると良いでしょう。
また梅干しは、肝機能をサポートする作用により二日酔いへの効果も期待できます。
飲酒前後に梅干しを食べたり、梅干しを使った料理をおつまみにしたりすると、二日酔いの予防や解消につながると考えられます。
梅干しの効果効能を健康・美容に活かそう

さまざまな栄養素や食品成分が含まれる梅干しは、健康や美容への効果・効能が期待できる食べ物です。
ご飯のお供に梅干しを添えて、健康づくりに役立ててみませんか?
15/e organicでは、梅の栽培時に農薬や化学肥料を使用していない梅干しを取り扱っています。
合成添加物も不使用であり、梅本来の味わいを楽しめます。
おいしい梅干しを食べながら健康づくりを進めたい方は、15/e organicで販売している梅干しをぜひお試しください。
まとめ
- 梅干しには、疲労回復や肝機能のサポートなどのさまざまな健康効果が期待できる
- 梅干しを毎日食べる場合は1日1粒までを目安にする
- 梅干しを食べるのは、運動前後、疲れを感じたとき、お酒を飲むときがおすすめ
【記事の監修】

15/e organic
栄養士 OKAYU
フィフティーンオーガニック表参道店でコスメや食品の接客を担当。
「一人でも多くの方に健康と美しさを届けたい」 その思いを胸に、15/e organicで活動しています。
栄養や美容に関する知識を活かし、皆さまに安心してご使用いただける製品を提供し、健康的な美しさを全力でサポートさせていただきます。